◆はじめに
「政策は日々、深化を遂げる」を指針に、2019年11月上旬日本最大規模の政策コンテスト第14回マニフェスト大賞のプレゼン・表彰式が東京六本木アカデミーヒルズで開催され、審査委員長である北川正恭早稲田大名誉教授は、今回で14回を迎えたマニフェスト大賞が過去最高の応募件数を記録し、初めての応募者が増えるなど「善政競争」の盛り上がりを感じ、また2019年4月の統一地方選挙では地方議会議員選挙の一部で政策ビラの頒布が解禁され、政策型選挙の環境整備が進んだ。加えて14年に公布された「まち・ひと・しごと創生法」(地方創生法)によって全国の自治体が作成した総合戦略は本年で最終年であるが、地域の課題解決に取り組む好事例が集まり広く共有することができた。マニフェスト大賞が今後とも政策のプラットホームとして進化し、各地の取組の進化とともに地方の自立を促し、地方から日本を変える大きな潮流となることを期待すると述べられた。
◆マニフェスト大賞「共生の心育つ公園づくり」
大賞・最優秀政策提言賞を受けた龍円愛梨東京都議(都民ファーストの会)は、2017年初当選の1回生議員、障害の有無にかかわらず子どもたちが共に遊べる安全な「インクルーシブ公園」の開設をマニフェストにまとめ東京都議会で提案した。一人一人の違いを評価して社会全体で包み込み、それぞれの魅力や強みを最大限引き出そうという「ダイバーシティ&インクルージョン」の実現を目指すとし、そうした考え方を浸透させるには「子どもの頃の経験が重要」だとして、こどもは公園での遊びを通じてコミュニケーションの方法を学び、障害のある子がいれば「一緒に遊ぶにはどうすればいいか」と考える。つまり心のバリアフリーは「共に育つ」ことで育まれるという子育て体験、信念を力説する。障がい児を育てるシングルマザー議員の提案は第1に障がいの有無にかかわらず、子どもたちが共に遊ぶことのできる公園であり(今年度末に都立砧公園に実現予定)、第2に子連れで安心して電車移動ができるように、車両内に「子育て応援スペース」を提案、要望書を都知事に提出して19年7月に都営地下鉄大江戸線に設置され運行開始された。第3に、仕事や育児等に忙しい世代も政治参加して意思を示せるようにネット環境を活用した。「親指で政治参画するICT活用」を提案、働き盛りの世代は忙しいとはいえスマートフォンやSNS等で発信することが多いので、短時間で政治参加する仕組みを作るべくインターネットアンケート調査を行い、11日間で集まった1500人以上の声を背景に芸術文化・子ども機能に期待する92%の声を届けた。3つのうち2つが実現、あと1つも具体的な行動力が評価された。
受賞者談話:民間テレビ放送局のアナウンサー・記者で得た「伝える」スキルを活用し、私自身がダウン症のある息子を育てるシングルマザーになったことで本当に困っている人は、助けてと声を上げる余裕や時間もないことを知った。今後もマイノリティの方々の声に寄り添い、「ちがい」がある人々も含めすべての方がその人らしく輝いてイキイキと生きていける社会の実現に向けて頑張っていこうと決意を新たにする。
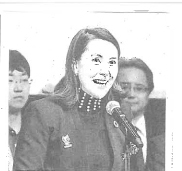
2019マニフェスト大賞
龍円愛梨東京都議、毎日新聞より
◆最優秀マニフェスト推進賞(首長部門)「住みやすい町目指して」
園田裕史長崎県大村市長は、かつて市議時代に政策提言賞を受賞しており、令和元年10月の2度目の市長選に当たり1期目のマニフェスト(27項目)は9割達成したと総括し、2期目のマニフェストとして待機児童解消やスポーツを生かしたまちづくりなど36項目を掲げて、その政策を詳しく説明したビラを作り会員制交流サイトや街頭演説などで訴え、無投票当選を果たす。大村氏は長崎県中央に位置し空港もあり、2022年度には九州新幹線開業も予定される県内13市で唯一人口が増え続けている。新マニフェストを市の総合計画に反映させ「県の玄関口である大村市の発展を牽引する」という強い気概を持って挑み続けたいと胸を張る。

最優秀マニフェスト推進賞(首長部門) 園田裕史大村市長
親交のあった松本崇元市長の案内で大村市を訪れた当時を思い出しつつ園田市長の取組概要のポイントをまとめると、「徹底的に政策・課題・制度設計・内容・実行・進捗・振り返り・全戸配布・デザインにこだわったマニフェスト政策のススメ」と言うことになろうか。彼は2015年市長選初当選の際に掲げた「マニフェスト2015」を、年度ごとに進捗状況報告書を全戸配布、4年間の任期終了に当たり最終的な報告書と合わせて新たに「マニフェスト2019」を発表し、4年間の政策実行進捗状況約9割達成及び進行を報告し、更に次の4年間の種まきと仕掛けを繋げて、広げて、カタチにする次の4年間への連続性を落とし込んだのである。彼の信条は「政治家の、特に首長の仕事は自らが政策を考え、書き、訴え、広げ、行動し、職員と市民と企業や団体と一緒になって実行する」ことだ。マニフェストは内容を全力で書き上げ字ばっかりの政策集、デザインとフレーズにこだわり、漫画や挿絵でなく読んでみたい、読みたくなるデザインと内容を目指して制作する。できたこと、できなかったこと、進行中・見直し・断念したことなどの内容を市民と共有し、徹底的・継続的・日常的にSNSで情報発信し、マニフェストの進捗情報、街頭演説、地区別ミーティング、市政報告会を現場でやり続けていく。市民みんなで、自分の住んでいる街のことに興味を持つ、声を上げる、参加する、広げる、オール大村の街づくりに挑戦し続けるとした。
彼の熱意溢れるプレゼンは、PDCAサイクルの確かな実践と市民目線の言動とに触れながら、会場にもまた一種の感動が広がったように感じた。こうした好実践例が数多く紹介され、それぞれの地域の個性・事情にマッチしながら政策進化していくことで「善政競争」が全国に広がり、地域から日本を変えていく動きに期待したいものである。
◆若者からの政策提言
(1)一般社団法人日本若者協議会(東京都)優秀マニフェスト進捗賞(市民部門)。
若者と議員の距離を縮める頼もしい若者たちがマンモス都市東京で輝いた。若者の意見が政策に反映されることを目指して、政治に直接声を届けられる仕組みを構築したのであった。その主役「日本若者協議会」は、「若者の意見を政策に反映させる団体」として、各政党への政策提言、協議を行う。2015年から日本版ユース・パーラメント
(若者議会)が、若者と議員がガチンコで議論する公開ディスカッションイベントを開催する。今年のユース・パーラメントでは、全7テーマを扱い、主要6政党(自民・公明・立民・国民・共産・維新の会)に対して、事前の勉強会等での分析や議論、当日参加者の意見を踏まえて政策提言する。計300名以上の若者の参加を得て多くの提言をマニフェストに反映させた。
当事者意識を持った政策提言:日本若者協議会は39歳以下を若者と定義し、小学生から30代の若者まで幅広く意見をまとめ提言する。現在、個人会員約270名、団体会員55団体(計4000名)、NPOの若者にも議論に参加してもらうなど実効性のある提言に努める。また現在「被選挙権年齢の18歳への引き下げ」を推進すべく全国キャンペーンを展開、大学・高校を国会議員などと回り、引き下げ対象の当事者である10代、20代前半の学生と意見交換、現時点で九州~東北の大学・高校など1000名近くの学生の意見を得た。
公約への反映:活動の中で特に意識しているのは、各党の公約に提言を反映させること。このため、事前に勉強会、会員同士の意見交換を重ね「現実的な」提言をまとめる。各党の担当者や議員に進捗を共有し継続してもらう体制を維持してもらう。結果、主要6党全党で多くの提言が公約に反映され、2018年5月には超党派で構成される若者政策推進議員連盟を発足し、法案実現に向けた勉強会や全国キャンペーンが盛り上がりつつある。
(2)若者と議員の距離を縮める:最優秀マニフェスト推進賞(市民)せんだい未来会議。
「理想の仙台市」について、10~30代の約800人を対象に街頭インタビューやアンケートを行い、政策提言集「仙台若者ビジョン提言集」を発表する。例えば「若者と高齢者のシェアハウスを設置する」「廃業する企業の特許を市が買収する」などといったユニークな施策を、郡和子市長や市議らに届けた。この団体は東北福祉大3年生(21歳)を中心に1年前に結成され市内大学生ら11人が活動している。共通する問題意識は「地方議員と住民の距離が遠いこと」。今年夏の仙台市議選前には立候補者を招いて若者と議論する場を設けるなど接点の少ない若者を中心とした市民と地方議員の距離を近づける活動を続ける。若者曰く「開かれた市議会になるよう、改革を市民の立場から進めたい」「総合計画の策定や選挙というイベントがある中で若者からアクションを起こせば、若者の政治離れを防ぐ一歩となるのでは」、そして「特に地方自治の現場は、アクションを起こせば短いスパンでフィードバックを得られる魅力的な舞台となり得る。私たちは地方自治の最前線で頑張る」と。

最優秀マニフェスト推進賞(市民部門)
せんだい未来会議
◆おわりに
私はマニフェスト大賞の初回から参加・関係させてもらっている幸せ者である。今回は、大賞と首長部門の最優秀賞及び関心の深い若者の政策提言と政治離れを防ぐ活動しか紹介できないのが残念だ。ノミネート数も年々増え、従来の議会、首長、市民から行政・自治体職員や報道機関、NPO、民間企業など多種多様な組織、異なる組織間の協働による取り組みなどに広がり、マニフェスト大賞が幅広いジャンルの組織や個人を巻き込み地方創生を目指すプラットホームとなってきた実感を覚える。これからも地方創生は、先ず、広い視野で何をもってその地域を輝かせるのか、その核となる資源やコンテンツを見極め、次には、実現に向けて的確かつ具体的なシナリオを描く、その上で、シナリオ実現に必要な意欲ある人材、内外の知見や先端技術を集め、関係者が当事者意識を以て志とスケジュールを共有して進むマニフェスト手法が必要となる。。
(西川政善、徳島文理大学総合政策学部(兼総合政策学研究科)教授)
|
|