◆第四次産業革命
青山学院大学青山キャンパスで開催された日本計画行政学会第40回全国大会において、この3月まで東京大学名誉教授であった坂村健東洋大名誉教授の講演を聞くことができた。2030年頃から本格化すると考えられる「第4次産業革命」についての講話を興味深く拝聴した。
ザックリと、カギとなる技術によって特徴づけると1800年代にイギリスに興った第一次産業革命は蒸気機関、次にアメリカを中心に内燃機関・電機モーターによる第二次産業革命、次のIT化事業分野(コンピューター、インターネット、パソコン等)もアメリカけん引の第3次産業革命、次なる2030年頃と考えられるAI(人口頭脳)による第4次産業革命の確実な出現に言及された。ここでもアメリカでの技術開発が急である。坂村名誉教授は、かしこい頭脳度向上、ロボット化、スマート化をあげ、さらなる人間社会の進歩を指摘する一方で、人間の雇用が奪われる雇用なき爆発的経済成長と裏腹に、人間に残される仕事はC(クリエイティブ)・M(マネジメント)・H(ホスピタリティ)に限りなく絞られるのではないかと指摘する。「IoTとAI(人口頭脳)で仕事が変わる」「フラットからオープンに」と言った現実に進行しつつある各国の事例を、自転車・自動車・医療・介護・汎用AI等の分野に分けて豊富な知見を述べ解説された。わが国もそれぞれに実績を上げているようだが、アメリカに次ぐ進歩に期待を込めたいとも述べた。
私の能力ではとても追いついて行けない最先端技術の世界であるが、わが国の将来が世界の未来につながる状況を目指してあらゆる可能性(教育・技術開発など)に積極的な対応を心がけたいものである。同時にこの時期のホットニュースとして東洋大生桐生選手100M9.98秒の大記録が全国を駆け抜け、会場では講演内容とともに突き抜けた高揚感を覚えさせたものである。
◆小池都知事の東京大改革
同じく招待講演の小池都知事の話。さっそうと会場に現れた知事は、スッキリしたファッションで笑みを浮かべ、まるで第一級のモデルが見せる歩調で登壇した。「都政におけるローカルガバナンス」を約45分間しゃべる。開口一番、「スッキリと都民皆様によって知事就任して一年」、「トップの頻繁な交替は行政の前倒しから抜け出せない」、「今がチャンス、東京大改革」、「激動の時代、世界の動きを知らないで世界の東京の位置づけはできない」と矢継ぎ早やにまくしたて、さらに「東京を変える事例を出してください(職員に対して)」、「議会が特に変わらない」、「スピード感を持って変えていこう」「これからは都市間競争の時代だ」などと熱弁を振るう。
また世界の大学ランキングで日本の大学が2ツしか入らない現実を踏まえ、大学のグローバルな競争の必要性を強調、であるのに東京23区内大学の定員抑制などはもってのほかだ、と手厳しい。
さて人口1300万人を起こすグレーター東京をどうするか。2020年の東京五輪・パラリンピックを活用、成功させ、次なる2025年をにらんで何をなすべきかと考えたい。
例えば多摩地区都市部で空家が820数万件、うち82万件が東京、これを街の財産にする、大学生の寮にする。ICT・IOTを介護・保育などの現場に持ち込む、テレワークの定着を図って都心に来ないで家で仕事ができる流れを作り働き方そのものを変えていく。そして「テレワーク、上はネクタイ、下ジャージ」の川柳まがいの状況を作っていく。つまり意識改革と制度改革、マインドチューニング・ちょっとしたことの改革で社会を変えていくことができるとした。
また、日本は女性の活かし方が下手だ。例えば都職員の4割が女性、管理職は2割、男女を問わず仕事のできる職場環境をを目指したい。都議会(127議席)中女性議員は36人、もっと増えて然るべきだろう。
さらにローカルガバナンスで重要なことはワイズ・スペンディング、都民の税金のかしこい支出である。あたりまえのことをあたりまえにする。このために公共情報70万件を公開し、緊張感をもってムダをなくしていく。これこそ東京大改革の1丁目1番地、都民ファーストなのだと強調した。
一方、1340万人の東京は、鳥取県58万人の約23倍、しかし他方で11の島がある。うち9つの島を訪問してきたし都内のあちこちで昭和ティックな所も多い。こうした所の個性ある地域社会づくり、待機児童対策・保育師確保・空家活用・子育てしやすい東京など目指したいとする。
またセーフティ対策として国道・都道で無電柱化を推進し、電線が乱立する環境からくる伝染病をなくしたい。さまざまな対策によって、スモークフリー(受動喫煙を回避)、エミッションフリー(脱大気汚染)、バリアフリーの東京を目指すとした。そのためには「行政も知恵比べ、時代の先を行く」と締めくくった。
 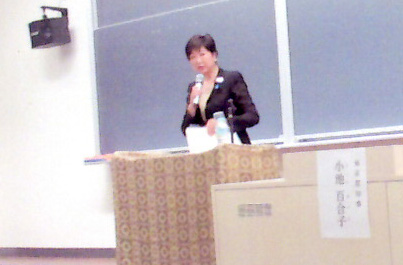
学会々場 小池百合子都知事
青山学院大学青山キャンパス 東京大改革を語る
◆首長が語るローカルガバナンス
人口減少時代を迎え、様々な行政課題が複雑に絡み合い、増殖することから、地方自治体のガバナンスは岐路にある。例えば、地域経済の停滞や人口減から派生する財政逼迫への対応、政策の世代間合意は成立するのか、都市化の進展に伴うコミュニティの機能低下に対して近隣同士のコミュニティ機能の再構築、これらに対する行政の関与のあり方、モータリゼーションの進展による郊外部への人口・諸施設の分散と中心部の空洞化、多機能型中心市街地を目指すコンパクトシティは限界集落の住民を市街地に誘導できるのか、教育を含む社会経済的格差がさらに分断社会を生み出さないか、などなど世代間や地域間の共感を困難にする多様な価値観から合意形成が難しくなっている。これらの難題解決に先進的な取り組みをする首長のシンポジウムの概要を以下記したい。
青山?東京都元副知事は地方自治体のガバナンスがどうあるべきかを考えるに当たって、ローカル(団体自治)とガバナンス(住民自治の視点)、憲法にわずか4条の地方自治の本旨と二元代表制を挙げる後藤新平初代東京市長は「自治は市民の中にある」として地域特性(地域から政策を出していく)の姿勢を紹介、海外では1980年代サッチャーやレーガン時代の改革、NPMへと進んできたことを紹介する。
東京では、1963年都知事交代(東都政→美濃部都政)から経済・ハード政策重視と生活重視・ソフト政策重視かの政策の振り子が繰り返されたことに及び、地方分権では第1次分権で国→地方、第2次県→市町村、第3次市町村→市町村民へという流れを指摘し、その中で日本初のガバナンスを主張されたのは「私の知る限り三鷹市であった」とされた。
受けて、三鷹市の清原慶子市長(4期目、全国市長会副会長)は、東京工業大で都市再生を研究し三鷹市の参加と協同のまちづくりのプラン策定にも関与しその後6代目市長に就任。不交付団体として「民・学・産・公(他自治体)・官(国)」ともに責任を担い合う「都市型産業(ITC・デジタル)」の誘致を推進、28人の議員とは多様な価値観をいかにまとめていくか、職員に対しては謙虚に学び続ける姿勢を求め、無作為抽出の市民審議会の活用を重視しているという。
田中大輔東京都中野区長は中央大の同窓で中野区職員出身、経営不在の区政を担って4期目、行政改革とガバナンス重視に徹しNPM手法を取り入れたPDCAサイクル、自治基本条例の下、稼げる区を目指して警察学校跡地や東映アニメーションの有効活用など文化・情報・人材の集積、さらなる産業化や経済成長策に取り組みたいとしている。基本計画策定時には市民300人の審議会で意見を聞き、その素案をパブリックコメントで補強、それを議会に送る過程をルーチン化した。区長は、東京23区と都で財政調整を行い都内区の平準化を狙うシステムを超えた施策展開によって、2040年には40%になる高齢化時代を見据えている。その諸施策を区民に根気強く説明し説得していく、それでも駄目な時には引っ張っていく覚悟で頑張ると頼もしい発言であった。
コンパクトシティで全国的に著名となった森雅志富山市長(5期目)も中央大同窓で古い付き合いである。一段とたくましくなった市長は「都市経営を重視する。耳ざわりのよいことを言うのはセールスマン、真の政治家は時には目指す方向に強制する必要もある。サッチャーがゆりかごから墓場までを65才まで、あとは自己責任とした決断も必要だ」とし、「人口減の時代、福祉では人を呼べない。総合力をつけること、家族が行くようなまちづくり(都市像)で雇用が生まれる。説得は極めて重要なキーワードだ」と力説した。また全国的に話題となった市議会の政治活動費問題については、「改選で38人中19人が新人となった。政治活動費のグレーゾーンが広がった。議会はしっかり議論と活動を徹底してもらい、決めるべき時に決め堂々巡りはしないことだ」と述べた。

シンポジウム(ローカルガバナンスについて)
左より細野中央大教授(司会)、青山元都副知事、清原三鷹市長、田中中野区長、森富山市長
(西川政善、徳島文理大学総合政策学部(兼総合政策学研究科)教授)
|
|